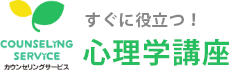いわゆる「都市伝説」をSNSで楽しむ方もいらっしゃるでしょう。
ここ最近は、「2025年7月○日に大災難が起きる」といった予言の話が流行っているようです。
かつて、「1999年7の月、空から恐怖の大王が降ってくる」というノストラダムスの大予言が社会現象になったことが思い出されます。
都市伝説を信じたくなるのには、どういった心理が働くのでしょうか。
●都市伝説とは
一般的に、都市伝説は誰が語り始めたのか情報源が曖昧で、口コミやSNSを通して拡散されます。
客観的な証拠はなく、語り継がれるうちに内容が変化していくことがあるようです。
事実ではない情報が広まる似たような現象に、フェイクニュースがあります。
フェイクニュースは情報発信者が虚偽の情報とわかっていて、何らかの目的をもって流す情報です。
一方の都市伝説は、スリルのある話や教訓となる話として語られ、情報発信者が虚偽だと思っていない場合もあるようです。
●都市伝説にひかれる心理的な理由
人はわからないことがあると不安になります。
例えば、近い未来に大災難がやってくるかもしれないという不安やオソレがあったとします。
都市伝説として具体的な物語になることで、「そういうことらしい」と理解して「安心したい」という欲求が関係している可能性があります。
また、他人が知らない話を知っているのは、ちょっとした優越感を満たし、都市伝説を口コミで広めていく理由にもなるでしょう。
それから、非日常的な物語で、現実には起こらないだろう不思議な話として、スリルや興奮を味わえる娯楽的な要素があることも、都市伝説にひかれる人がいる理由でしょう。
●都市伝説を信じる心理
ひとつは、確証バイアスです。
人は自分が信じている内容に沿った情報を集めやすく、反対の情報を過小評価する傾向があります。
AIの活用により、ユーザーの興味関心に沿った情報が集まりやすくなっていることも、情報の偏りを大きくする要因でしょう。
もうひとつは、利用可能性ヒューリスティックの影響です。
ヒューリスティックとは、いわゆる経験則のようなもので、効率的に答えを出すために、誰もが無意識に行っているものです。
利用可能性ヒューリスティックは、記憶に残りやすく、思い出しやすい情報ほど、発生頻度が高いと判断してしまう傾向です。
都市伝説はインパクトのある話が多いため、影響をうけやすいのです。
もうひとつは、いわゆる集団心理で、集団の雰囲気や多数派の意見に流されて、合理的な判断ができなくなる状況があります。
また、他の人と同じように考えたり動いたりしようとする同調性や同調圧力が働く場合もあるでしょう。
●世界が滅ぶ話が繰り返し話題になるのは
世界が滅ぶ話は、各地の文化で繰り返し話題になりやすいテーマです。
日本では、平安時代末期に末法思想(釈迦の入滅から○年後に仏教が衰退して社会が混乱するという考え)が広まり、いくつもの鎌倉新仏教を生み出した歴史もあります。
近い未来に絶望していると、世界が滅ぶ話は現実から逃避するのを正当化する理由となるでしょう。
あるいは、今現在に不満を抱えている人たちの変化への願望が、破壊と再生の物語を欲することもあるでしょう。
また、共通の境遇を想定することで、仲間意識や連帯感が生まれやすくなります。
つながりを求める心理、孤独を抜け出したい心理なども関連があるのでしょう。
世界が滅ぶ話題は、現状に満足していない人たちに、ポジティブな何かを与えているのかもしれません。
そして、世界が滅ぶ話を信じたいのだとしたら、何かしら「変化」を望んでいると考えてみてもいいのかもしれません。
●都市伝説の教訓性
都市伝説は怖い話や奇妙な話であるのと同時に、そこには何らかの教訓が含まれています。
例えば、口裂け女の話。
マスクで顔を隠した女が「私、きれい?」と尋ね、口が裂けている姿を見せて襲いかかるという都市伝説です。
これには、見知らぬ人に注意すること、外見に惑わされないといった教訓があります。
大災難の都市伝説は、自然災害を正しく恐れる教訓となるでしょう。
非常食の備蓄、避難経路の確認、家族との連絡方法の共有など、具体的な行動を促すきっかけとなっているのです。
●都市伝説にふりまわされないで
今回は、都市伝説を信じたくなる心理についてまとめてみました。
都市伝説を鵜呑みにして、必要以上に恐れないでいただければと思います。
私たちの行動が未来を作ります。自分たちで変えていけることがあると信じて、地に足をつけて落ち着きましょう。
都市伝説をエンターテイメントとして楽しみながら、教訓部分は活かし、正確で信憑性のある科学的な情報に基づいて行動したいと、私は思います。