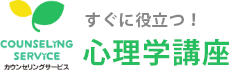仕事上、上司が部下に対して指導やミスを指摘しなければならないことがあります。
会社に損失を与えるほどのミスがあったり、取引先や同じ部署の人たちに迷惑をかけてしまったり。
大きなミスからさほど問題にならないものもあり、今後部下が仕事を進めるうえで必要だと思えば指摘することがあります。
けれど上司が優しく伝えたとしても人によっては落ち込んでしまうことがあるのです。
部下が落ち込んでしまうと上司が罪悪感を持ってしまい、再び部下がミスしたときに指摘しづらくなる場合があります。
だからといって、そのまま見過ごすわけにもいかない。
今回は、注意や指導をするたびに落ち込んでしまう部下に対してどのように接すればいいのかについてお伝えします。
*****
自分のミスや失敗で落ち込む人は少なくありません。
また上司に指摘され落ち込むこともよく伺います。
仕事のみならず日常生活でもミスは起こり、対人関係では誰かに指摘されることがありますが、その経験を自分の成長につなげる人もいるのです。
両者の違いは起きた出来事の原因の捉え方が考えられます。
人がミスや指摘を受けたとき、その原因を自分のせいにすることは多いのですが、
落ち込む人は、
「自分には能力がない」
「能力がないからうまくできるはずがない」
「仕事が合っていない、向いていない」+
と原因を自分の能力や適性のせいにしがちだったりします。
一方成長につなげる人は、
「努力が足りなかった」
「勉強不足だった」
「体の調子がよくなかった」
など努力やスキル不足、その時のコンディションが原因と捉えるようなのです。
能力や適性は急に変えることが難しいと思い落ち込む。
努力やスキル、コンディションなどは努力して技術や知識を磨けば伸ばすことができる。
改善の余地があると考えられるので前向きになれるのかもしれません。
*****
ミスや指摘は注意すべきところや不足などを指し示しているのですが、落ち込みやすい人は責められたように感じます。
ミスをして周りに迷惑をかけてしまったと自分を責めているところに上司に責められたとなればより仕事へのモチベーションも下がるでしょう。
自分の能力や適性のせいにしている部下に対しては、改善の余地があること伝え、失敗やミスがなぜ起きたのかを聞き取り、その背景を理解したうえで未然に防ぐ方法を一緒に考えてあげるといいかもしれません。
例えば、業務内容がよく理解できず曖昧な状態のまま進めてしまった結果ミスや指摘につながったとしましょう。
上司や同僚などの周りの人に聞くこともできるのですが、落ち込みやすい人の場合は、
「忙しい時に皆の手を煩わせてはいけない」と周りの人を気遣っていたり
「これぐらいのことも理解できていない人と笑われるかもしれない」
「同じことを聞くと怒られるかもしれない」
と自分に対するまわりからの評価を気にして、もう一度聞くことを怖れていることが少なくありません。
聞けない事情があるかもしれないという前提で、曖昧なことがあれば周りの人に聞く・確認することをあらためて伝えること。
上司の寄り添い方によって部下の心が救われるように感じ、仕事への意欲を引き出すことにつながるかもしれません。