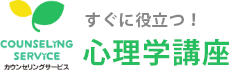仕事では、するべき事がきちんと出来ていて、ミスなく確実に業務を進めていくことが求められますが、何らかのミスがあると厳しく指摘をされることも多いのではないかと思います。
99.999%問題なくても褒められる事はなく、0.001%のミスで叱られる。
ミスしないように努力を重ねてきても、一度のミスですべて溶けて無くなってしまうような感覚になったこともあるかもしれませんね。
仕方がないとはわかっている。
でも、いつも怒られてばかりでしんどいな、頑張っている姿は見つけてくれないのかな。
そう思うことはおかしくないと思いますし、私がこの仕事をしなくてもいいのではないか、と感じてしまうことがあっても不思議ではないと思います。
今回は、
・なぜ褒められる事が少ないのか
・叱られてばかりだ、と感じてしまう心の仕組み
・普段の仕事の中で頑張っている私の見つけ方
以上の3点をご紹介します。
+
【なぜ褒められる事が少ないのか】
〜出来ていることがあたりまえ、という職場の雰囲気があるかもしれません〜
私自身が会社員時代に感じていたことではありますが、ミスなく出来ていることがあたりまえで褒められることがないけれど、1つのミスに対してしっかりと叱られると感じる事はないでしょうか。
こういった雰囲気の職場は珍しくないようです。
その理由としては、以下の事が考えられます。
・減点主義、出来ていないことにフォーカスされる
たとえば、減点主義が背景にあることがあります。
多くの職場では問題が発生したり、ミスが発生した際に注目が集まりやすく、それらが減点の対象になることがあります。
一方で、問題なく業務が進められていたり、期待通りの成果が出ていても「ゼロ」「当たり前」と扱われ、注目となりにくいようですね。
そのため、確実に業務をこなすことが評価の対象になりにくく、褒めたりすることも少ないようです。
・日本人特有の文化も影響している
また、日本人特有の謙遜する文化も影響しているかもしれません。
褒める側、褒められる側も、賞賛を避ける傾向が強いため、褒める時も「よくできてるじゃないか」程度に控えめなことも多いようですので、褒められている実感を感じにくかったり、たとえ大きく賞賛されたとしても「私はまだまだ」「たまたまなので」と謙遜して受け取れていない事も影響しているようです。
【叱られてばかりだ、と感じてしまう心の仕組み】
・認知の歪みと、ネガティビティ・バイアスについて
私達が仕事を進めていく中では決して叱られることばかりではなく、時に楽しく雑談したり、誰かの優しさに触れたり、誰かを気遣ったり、気遣われたり。
嫌なことばかりではないはずなのですが、ネガティブな出来事に思考が集中するのは理由があるようです。
・認知の歪み
認知の歪みとは、物事の受け止め方や解釈に偏りが生じる心理的な現象で、物事の見方や思考のクセのようなもの。
事実を客観的に捉えるのではなく、自分自身の主観で物事を歪めて捉えてしまうこと。
・ネガティビティ・バイアス
ネガティビティ・バイアスとは、人がポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意を向けやすく、記憶に残りやすい心理の傾向を表します。
〜ネガティビティ・バイアスによって認知の歪みを促進させることがある〜
例えば、仕事でミスをしたときにネガティビティ・バイアスによってミスに心がとらわれてしまうと、「自分は”また”ミスをした」という認知の歪みが生じて(客観的にみれば、ただ一つのミスに過ぎない)その認知の歪みが、より強いネガティビティ・バイアスになり、さらに強い認知の歪みを生む、という悪循環に陥ることがあります。
この悪循環がネガティブな思考を繰り返してしまい、抜け出せなくなってしまいます。
やがて、自分ばっかり損だな、こんなこと意味あるのかな、などといった思考も繰り返されてしまい、自信を失ってしんどくなってしまうようです。
【普段の仕事の中で頑張っている私の見つけ方】
〜自分自身の認知の歪みに気づき、頑張りに気づいていくために〜
※認知の歪みはどんな人も多かれ少なかれ持っているものなので、歪みがあるからと言って自分が悪い、情けない、というわけではないことをご承知おきくださいね。
・自分の感情を意識してみる
不安や悲しみ、罪悪感などを感じると、きちんと出来ていないのではないか、受け入れられていないのではないか、自分が悪いのではないか、という認知の歪みが起きやすくなります。
ネガティブな思考が頭を駆け巡るときは、自分自身が今どのような感情を感じているのか、内観(心の中を感じる)してみることもおすすめですよ。
感情とは、不安、恐れ、悲しみ、寂しさ、怒り、罪悪感(私が悪いと思う)などです。
・自動的に思考する言葉をキャッチしてみる
自動的な思考とは、意識せずに頭の中にパッと浮かんでくる考えのことです。
「〜すべき」「〜に違いない」「どうせ〜だ」など、断定的な言い回しや、「いつも〜」「全く〜」など、白黒はっきりさせるような極端な表現は客観的ではなく、主観的で思い込みによる認知の歪みが起きやすいようです。
・第三者の視点を取り入れる
信頼できる上司や、同僚、カウンセラーなど、信頼できる人に相談することで、相手がどう感じるか、どう考えるか聞いてみます。
客観的な意見は、認知の歪みに気づくきっかけなることがあります。
また、「もし仲間だったらどうアドバイスするか?」と考えることで、客観的な思考を取り戻す事も期待できますよ。
同じように「仲間にかけてあげたい応援の言葉」を考えることで、自分の頑張りを再確認することも可能です。
・仲間の頑張りを応援したり、褒めていく
仲間の失敗に目くじらを立ててしまうことはありませんか?
他人の失敗を受容出来ないときは、自分自身の失敗もまた受容することが難しいようです。
その結果、「私はまだまだ」「甘えてはいけない」と自分に厳しくなりすぎてしまうことも。
同僚など仲間の頑張りを褒めたり、支え合いを意識することで、仲間の失敗に寛容になり、仲間からも応援、賞賛されやすくなることが期待できます(好意の返報性)
また、自分自身の頑張りに気づき、寛容になることにより自己価値や存在価値を肯定するきっかけにもなりますよ。
・さいごに・
社会生活の中では、ミスやそれに伴う叱責、評価への影響はどうしても避けて通れない事も多いと思いますが
毎日仕事に通うことは、決してあたりまえのことではなく日々の頑張りの積み重ねが実り続けている事、成功している事なのだと私は思います。
皆様の日々の成功を、心より応援致します。