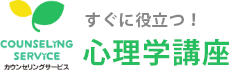母子癒着に気づくところから人生は変わり始める
母子癒着とは何か、その正体に気づくことで「私は私」として生きるスタートが始まります。
◆母子癒着ってどういうこと?
母子癒着という言葉、聞いたことがあるでしょうか?
一言でいえば、母と心理的に距離が近すぎる状態のこと。
「お母さんがどう思うか」が、無意識に自分の行動や気持ちを決める基準になってしまう状態です。本人はそれを“普通”と思っていることが多いため、気づきにくいのも特徴です。
たとえば、こんなことに心当たりはありませんか?
・何かを決めるとき、「お母さんにどう思われるかな」が頭をよぎる
・母をがっかりさせたくなくて、自分の本音を抑えてしまう
・母が困っていると、自分のことのように苦しくなる
・母から距離を取りたくても、罪悪感が強くてできない
こうした感覚があると、人生の舵取りが「自分」ではなく「母の気持ち」になっていきます。自分で選んだつもりの進路、仕事、恋愛さえも、じつは「母が喜びそうだから」「母が納得しそうだから」という理由で選んでいた、ということも珍しくありません。
自分の気持ちを感じにくくなるというのも、癒着の大きな特徴です。それは、まるで自分の輪郭がぼやけてしまったような感覚です。自分がどこにいるのか、何を望んでいるのかが見えにくくなっていきます。
◆仲が良いのと癒着は違う
誤解されやすいのですが、「母と仲が良い=癒着」ではありません。癒着とは、母の感情や期待が自分の心に過剰に入り込んでいて、自分の気持ちが後回しになってしまう状態です。
母との関係に悩む方の中には「母は優しかった」「特に厳しくなかった」とおっしゃる方も多いです。でも、癒着の鍵は“母がどうだったか”より“自分がどう感じていたか”にあります。
母が意識的に支配したわけではなくても、子どもが自然と“母を優先することが愛”と感じ取り、そう行動してしまっていた場合、それも癒着にあたります。
「母の期待に応えなければいけない」
「母の負担にならないようにしなければいけない」
そんなふうに感じていたなら、無意識に母のニーズを優先する生き方が身についている可能性があります。そうすると、自分の欲求を後回しにすることが習慣になり、「本当はどうしたいのか」が分からなくなっていきます。
そして「いい子だった私は、今もどこかで“母に褒めてもらいたい私”のままなのかもしれない」と、ふと気づく瞬間があるのです。
◆癒着の影響はどこに出る?
癒着の影響は、日常のささいなところに表れます。たとえば…
・人の期待に応えようと無理をしすぎる
・自分の意見がわからない
・恋愛で「見捨てられないように」と相手に合わせすぎる
・人の顔色をうかがってばかりで疲れてしまう
・一人の時間に罪悪感を感じてしまう
・自分の選択に常に「これでよかったのかな?」と不安になる
こうした生きづらさの根っこに、母子癒着がある場合もあります。でもそれは、母に愛されたい、がっかりされたくない、という健気な気持ちが土台になっていることがほとんどです。
特に恋愛では、母との関係性が色濃く出ることがあります。母の顔色をうかがって生きてきた人は、恋人やパートナーにも同じように“機嫌を損ねないように”“嫌われないように”と無意識に気を配り続けてしまうのです。
結果として、相手に尽くしすぎてしまったり、言いたいことが言えずに我慢を続けたりと、関係のバランスが崩れてしまうことがあります。
だからこそ、「私ってダメだ」と責めるのではなく、「私は、愛されようと一生懸命だったんだね」と自分に言ってあげてほしいのです。そのやさしさが、自分を癒すスタートになります。
◆気づくことから人生は変わりはじめる
母子癒着は“すぐに手放すべきもの”ではありません。でも、「少し苦しいな」と感じたときは、自分に問いかけてみてください。
「私はどうしたい?」
「これ、本当に私の気持ち?」
こうして自分の内側に目を向けるだけでも、少しずつ心の輪郭が戻ってきます。
母を否定するのではなく、自分の感情にOKを出す。その小さな一歩が、「私は私」として生きる第一歩になります。
母を大切に思う気持ちと、自分を大切にすることは、矛盾しません。むしろ、自分の心を守ることができて初めて、健やかな親子関係を築くことができるのです。
癒着に気づいたあなたは、すでに一歩踏み出しています。ここからは、少しずつで大丈夫。自分の声を聴き、自分の気持ちを取り戻していく時間を、どうか自分に与えてあげてください。
次回は、「“いい子”をやめたくてもやめられない」というテーマで、幼い頃に身につけた“がんばりぐせ”について一緒に見ていきましょう。
(続)