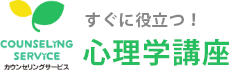子どもを追い詰める言葉
「早くしなさい」
ある朝、テレビを見ていたら「早くしなさい」が、子どもが親に言われて一番嫌な言葉第一位だというのを聞いて「うわ〜、言ってたー」と思ったことがありました。
振り返ると私は、子どもが小さな頃から大人になっても「早くしなさい」を言っていたことを思い出して少々落ち込んだのですが。。。
「この子はこんなにのんびりしていて、大丈夫だろうか?」
「もっと言い聞かせた方がいいのでは?」
そんな、子どもを心配する気持ちに急かされて、つい口調がキツくなることってあるかと思います。
子どもは”自分のペース”を探している
小学生の低学年の頃までは素直に親の言うことを聞いてくれていても、思春期に入ると子どもの態度がガラッと変わることがあります。
口をきかなくなったり、返事は「別に」か「フツー」だったり。
けれど、思春期は「自立の準備期間」でいわゆる『アイデンティティの確立』の時期。
親の価値観から一旦距離を取り「自分は何者か」を模索する時期なのですね。
その過程で子どもは、迷ったり立ち止まったり遠回りすることが当たり前のように起きます。
けれど、親は人生経験があるのである程度の先がみえてしまう。
なので、子どもがのほほんとしているとつい「今からしておかないとあとで困るよ」「前もって準備しておきなさい」などと言いたくなるし、実際に言ってしまうことも。
でも、その焦りは親の時間感覚で、子どもはまだ“自分の時間”の中にいるのです。
追い詰められると感じると閉じる心
人は「自分で選んでいる」と感じる時に最も力を発揮するといいます。
「自律性」が満たされることが成長の鍵なのです。
子ども自身が決めた目標やルールに従って自分自身を律して行動することが、自己肯定や自信につながるのですね。
ところが、ついつい私たち多くの親が言ってしまいがちな「早くしなさい」。
急かされた子どもは
「どうせ自分はダメだ」
「何を言っても/しても否定される」
「親の期待に応えなければ」
そう感じて本音を隠し始めたり無気力になったり反発したり。
親としては、子どもを心配する不安から出た言葉が、子どもの心を縮こまらせてしまうこともあるのですね。
親が焦るのはなぜ?
親の焦りの気持ちの奥には子どもに対する愛情があります。
「失敗してほしくない」
「傷ついてほしくない」
「将来困らないようにしてあげたい」
そのためには
「今、なんとかしないと」
「今から準備しておかないと」
という心配。
大切に思うからこそ、転ばぬ先の杖になってあげたいです。
そして、もうひとつは親自身も急かされて育ってきたという場合。
「ちゃんとしなさい」
「早くしなさい」
「そんなことでどうするの」
そう言われてきた記憶が無意識に繰り返されていることもよくあります。
私も度々そのように親から言われていましたが、言われるたびにウンザリしていたのを思い出します。
「心配してくれているんだろうけど、放っておいて」
「親が言うことは正しいんだろうけど、そんなに上手く進めない」
とよく思っていました。
けれど、普段はそんなことは忘れて我が子には同じようなことを言っていたので自分の無意識に気づくことって大事なことです。
子どもに必要なのは「正解」より「安心」という土台。
親がどっしり構えて「あなたのペースでいいよ」と受け容れてあげていると、それが子どもの安心という土台になります。
いつでも戻れる場所がある
「あなたのペースでいいよ」と受け容れることが子どもの安心につながりますが、なにも言わないことが良いわけではありません。
言っていいことと悪いこと。
していいこととしてはいけないこと。
日常の学校や家でのルールを守ることも必要ですものね。
なにか引っ掛かることがあったときに「そんなことではダメだ」と否定したり「そんなときはこうするべき」とコントロールするのではなく「お母さんはこう感じるよ」とだけ伝えることの方が、子ども自身が考える余白をもたらします。
「早く改めさせないと」
「早くわからせないと」
と思ってしまいがちですが、親の役割は子どもを早く自分と同じレベルに引き上げるための時計になることでも、無理やり針を進めることでもありません。
子どもが歩いている暗い道の少し後ろを、灯りを持って歩くことかなと思います。
子どもは子どもの時間で進んでいて、芽が出て花が咲き実がなる季節はそれぞれ違います。
親自身も焦ったり心配で眠れない時期もあるかもしれません。
でもそれは子どもを大切に思っているから、ある意味当然です。
けれど、子どもは子どものペースで進んでいると信じる。
その子どもを応援、援助すること。
そんな姿勢が子どもの安心で安全な場所になり、子どもは子どものペースで自分の足でちゃんと歩き出す。
もう、すっかり大人になった我が子を見ていて、今はそう感じています。
「わかってはいるけど、つい口出ししてしまう」
もし今、そうやって自分を責めていたとしても大丈夫です。
毎日子どもと向き合い、子どものためにとがんばっているあなたの愛情を子どもはどこかでちゃんと感じているから。
けれど、ひとりで抱えきれないときは信頼できる人に頼ったり、カウンセリングもご活用くださいね。
子育てって喜びも大きいけれど、その分迷いや不安も大きいもの。
そんなときはぜひ頼ってください。
あなたの安心や安全の場になれたら嬉しいです。
*
来週は、のひらさち絵カウンセラーがお送りいたします。
いつも穏やかでふんわりした包容力が魅力のカウンセラーです。
どうぞ、お楽しみに♪