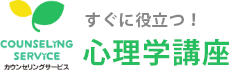「比べてしまう心には、“安心したい”という本能がある」
それは人の心が「安心したい」と願う仕組みの表れでもあります。
この回では、比べずにいられない心理の背景についてお伝えします。
友人の昇進報告、誰かの幸せそうな投稿、軽やかに見える暮らし。
それを見た瞬間、心の奥でチクリと痛みが走る。
「私、何をやってるんだろう」と焦りや劣等感が顔を出す。
でも、それは意志が弱いからでも、性格がねじれているからでもありません。
実は、人間に本来備わった“生存の仕組み”が働いているのです。
私たちが他人と自分を比べるのは、「安心したい」から。
昔、人が群れで生きていた時代、周囲と大きく違う行動を取ることは危険でした。
「みんなと同じようにしていれば安全」そうした本能的な感覚が、今も私たちの中に残っています。
つまり「比較する」は、もともと命を守るための“確認行動”だったのです。
ところが現代では、この比較が安全のためではなく、**自分の価値を測るため**に使われるようになりました。
「誰かより優れている」「誰かより遅れている」その基準を、他人に明け渡してしまっている。
これが、心の苦しさの正体です。
SNSが日常になった今、比較の機会は一気に増えました。
そこでは、人の“よい瞬間”だけが切り取られ、延々と流れてきます。
仕事の成功、楽しそうな集まり、整った部屋、笑顔の写真。
それらは確かにその人の現実ですが、同時に「編集された現実」でもあります。
そして私たちは、自分の“素のままの日常”と、“他人のベストショット”を比べてしまうのです。
「私は何をしてるんだろう」「あの人はいつも幸せそうなのに」。
そう感じるのは、自然なこと。
でもそのたびに、心の中では見えない競争が始まり、心の安定が失われていきます。
SNSの怖いところは、“見られる”ことが前提になっている点です。
見られることが価値になり、反応が自分の存在証明になる。
「いいね」が多ければ安心し、少なければ落ち込む。
まるで他人の指先ひとつが、自分の評価を左右するかのようです。
本来、比較は「違いを知るためのもの」でした。
けれどいつの間にか、「どちらが上か」を決める道具になってしまった。
そしてその基準は、ほとんどが他人の目線から作られています。
誰かの基準に合わせて自分を採点している限り、心は休まりません。
どんなに頑張っても、上には上がいる。
比較のスイッチが入ったままだと、どんな成果を得ても「まだ足りない」と感じてしまう。
まるでゴールが遠ざかるマラソンのように、永遠に「もっと」を追い続けてしまうのです。
でも、比べることそのものが悪いわけではありません。
比べることができるからこそ、人は学び、選び、進化してきたのです。
大切なのは、「何のために比べているのか」を意識すること。
たとえば、誰かを見て「羨ましい」と感じたとき。
それは「自分もそうなりたい」という“願いのサイン”かもしれません。
憧れの裏側には、まだ自分が見つけていない可能性が隠れています。
また、モヤモヤや苛立ちの中には、「私はこのことを頑張りすぎている」「無理をしている」というサインが潜んでいることもあります。
比べて落ち込むのではなく、比べたことで“自分の心の動き”に気づく。
それができるようになると、比較はあなたを苦しめるものではなく、
“自分を理解するレーダー”に変わっていきます。
そしてもうひとつ大切なのは、「比べたあと、自分にどんな言葉をかけるか」です。
「私はまだダメだ」「あの人はすごいな」で終わらせるのではなく、
その後に「でも、ここまではやってきた」「私は私のペースで進んでいる」を添えてください。
ほんの一言でも、その積み重ねが“自分の軸”を取り戻す力になります。
私たちは比べることをやめられません。
けれど、比べ方を変えることはできます。
比べるたびに、自分の価値を失うのではなく、自分を少し理解できるようになる。
比較の痛みの中には、実は「自分がどう生きたいか」という願いが隠れています。
それを見つけられたとき、
比較はもう敵ではなく、あなたの味方なります。
(続)