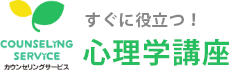また淋しい思いをするぐらいだったら、だれにも依存したくない
こんにちは 平です。
彼女はとてもしっかりとした女性でした。
ご両親は彼女が3歳のときに離婚。以来、母親と二人で暮らすようになったのですが、母親はそのときから始めた仕事で大成功し、多忙であったため、家にいる時間はわずかでした。
よって、彼女は自立した子ども時代を送り、だれかが自分を喜ばせ、心を満たしてくれるという経験はほとんどしたことがなかったのです。
学生時代からの彼女の口ぐせは、「そんなことぐらい、自分でしろよ」。彼女自身、そうして育ってきましたから、それが当たり前のことだったのです。
また、女性的な部分より男性的な部分のほうが強い母親に育てられた彼女も、やはり男性的なものの見方・考え方をするタイプでした。
そんな彼女が男性に心を動かされるということはほとんどありませんでしたが、あるとき、彼女のことを猛烈に好きになってくれる人が現れたのです。
そして、母親の「自分を愛してくれる人と結婚したほうが、女は幸せになれるのよ」というひとことで、その男性と結婚することにしたのです。
しかし、ご主人は彼女と一緒にいて、「妻は自分にあまり興味をもっていない」と感じたようでした。
そのため、彼女を束縛しようとしたり、彼女が関心をもつ人やものに嫉妬したりするようになったことから、この結婚は1年で破綻したのです。
彼女は、だれかに甘えるという経験をしたことがまったくなく、そのために、人から甘えられるということもうまく理解できませんでした。
ですから、将来、自分が子どもをもったとき、その子どもが自分に甘えてきても、「そんなことぐらい、自分でしろよ」と言ってしまいそうで、そんな自分に嫌悪感をもっていたようです。
といっても、子どもだったときの彼女が、親に甘えたがらなかったわけではありません。
甘えたかったときに、甘えさせてもらえる環境ではなかったわけで、そこには大きすぎるといっても過言ではない痛みがありました。
その痛みを感じないようにという努力を彼女は子どものころからしてきたわけで、その抑圧した感情は岩のように堅固なものになっていたのです。
彼女に聞きました。
「あなたが、言われていちばんいやなことはなんですか?」
「父親がいないことで、同情されることです」
彼女の母親は、父親がいないことで彼女に肩身の狭い思いをさせないようにといつも気を配っていたようで、それを感じていた彼女もそれを負い目にしたくないと思っていたのです。
しかしながら、この父親がいないということが、彼女の心のいちばん深い部分に居座っていたのです。
そこで、カウンセリングではちょっとしたインナーチャイルド系のワークを行ってみました。
イメージの中で、子どものときの自分自身に会ってもらったのです。
そこには、小学校2年生ぐらいのとても勝ち気な女の子がいました。
そして、その女の子にこう言ってもらいました。
「私にはおとうさんがいないの」
大人になった彼女の人格にとって、それを口に出すことはタブーでした。しかし、小学校2年生のときの彼女なら、それは言ってもいいことだったのです。
「私にはおとうさんがいないの」
女の子がこの言葉を3回言ったところで、大人の彼女は爆発したように泣きはじめました。
小学校2年生の女の子をイメージの中で抱きしめ、彼女は号泣したのです。
「また淋しい思いをするぐらいだったら、だれにも依存したくない」
そう思うほど、彼女はだれかに失望し、傷ついた経験をもっていたわけです。
そして、その“淋しい”という言葉が、彼女にとってはタブーとなっていたようでした。
その後、彼女はうちのスクールに通い出したのですが、私は彼女と目が合うたびに、「淋しいなんて感情を思い出させやがって!」とにらまれることになったのです。
では、来週の『恋愛心理学』もお楽しみに!!