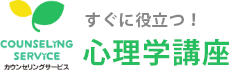支える人も、頼る人も、本当はつながりを求めていた。
支える側・頼る側の双方に潜む「怖れ」や「役割への執着」を心理的に解説し、自分自身との健全なつながりを回復するヒントを探ります。
■ “本音”が言えない共依存の構造
共依存の関係では、感情やニーズを抑え込み、「本音を言わない(言えない)」というパターンが頻繁に見られます。これは“気を使っている”という表面的な話にとどまらず、心理的な防衛反応として根深く存在しています。
・「本音を言えば、相手を傷つけるのでは」
・「気持ちを伝えたら、嫌われるのでは」
・「感情を出したら、関係が壊れてしまうのでは」
こういった恐れは、幼少期の親子関係や、過去の人間関係での痛みから来ていることがあります。
たとえば、「泣くと怒られた」「わがままは許されなかった」「親の顔色を見て育った」という体験は、自分の感情や欲求を“隠す”という反応を学習させます。大人になってからも、その反応は関係性の中に持ち込まれやすくなるのです。
■ “支える側”にある感情の抑圧
支える側の人は、自分を後回しにし、相手のために尽くすことに過剰な価値を置きがちです。
・相手の言動に腹が立っても、「そんなことを思う自分は悪い」と感じてしまう
・感謝されないことが続いても、「相手は余裕がないから仕方ない」と自分に言い聞かせる
・自分が疲れていても、「私が我慢すれば済む」と押し殺す
こうして自分の気持ちや境界線を無視し続けることが、結果としてストレスの蓄積・体調不良・情緒不安定につながることもあります。
■ “頼る側”にもある葛藤と不自由さ
共依存では、“頼る側”にも特有の葛藤があります。
・経済的に依存していて、自分で生活を立て直す力がない
・仕事が続かず、周囲の支援を当然のように受けてしまっている
・精神的に不安定で、誰かに話を聞いてもらえないと崩れそうになる
・罪悪感を抱えながらも、支えてくれる人から離れられない
このように、“頼る”側にもまた、無力感・自己否定感・依存不安などの複雑な感情が存在しています。
さらに、頼ることで関係性を維持している場合、「距離を取った方がいい」と思っても、自立に踏み切れない——という内的葛藤に苦しむことも少なくありません。
■ 本音を言わない理由は「関係を壊したくないから」
共依存の関係にある人たちは、関係性を壊したくないがゆえに、自分の感情・欲求・限界を抑えるという方法を選んでいます。
・「もう疲れた、やめたい」と思っても、相手が困るからと口をつぐむ
・「もっと私を見てほしい」と思っても、相手の重荷になりたくないから我慢する
・「私ばっかり助けてもらっている」と思っても、恩を仇で返す気がして言い出せない
つまり、本音を言うこと=関係を壊すことという認知があるため、言わない・言えないという選択になるのです。
■ 本音を伝えるために必要な“内的境界線”
共依存から抜け出すには、まず自分の内側にある「境界線」を明確にする必要があります。
「これは私の感情」「これは相手の課題」
「ここまでは支援できる」「ここから先は無理がある」
「これは望んでいること」「これは我慢しているだけ」
このように、自分と他者の感情を心理的に分けて感じる力(=内的境界線)がなければ、関係性の中で自分がすり減ってしまいます。
■ 「本音=相手を攻撃すること」ではない
多くの人が、本音を伝えることにためらいを感じるのは、それが相手を責めることのように感じられるからです。
けれど、心理的に健全な本音とは、「あなたが悪い」ではなく、「私はこう感じている」を伝えること。
・「私は、最近とても疲れていると感じています」
・「私は、頼りにされることは嬉しいけれど、少しプレッシャーも感じています」
・「私は、もう少し対等な関係を築けたら嬉しいと思っています」
このように、自分の感情や願いを主語にして話す(=Iメッセージ)ができれば、本音は関係性の破壊ではなく、関係を深める手段になり得ます。
■ 共依存の終わり=“孤立”ではなく、“自立と共感の両立”
「共依存をやめる」というと、「もう誰も頼らない」「一人で生きる」と極端な方向へ向かいがちですが、それは誤解です。
共依存をほどくとは、「自立」や「感情の分離」を手に入れたうえで、対等なつながりを築くというプロセスです。
・自分のニーズも、相手のニーズも大切にする
・過剰に介入せず、過剰に放置もしない
・支え合うけれど、支配しない・されない
このような関係性は、「境界線を持ち、本音を伝え合う」ことでしか育ちません。
■ まとめ
本音が言えない関係は、静かに、そして確実に心をむしばんでいきます。
でも、共依存を抜け出すことは、決して“関係を断ち切る”ことではありません。
むしろ、“本当の意味でつながる”ための道なのです。
感情を、欲求を、限界を、少しずつ言葉にしていく。
その一歩一歩が、自分を大切にし、相手との関係を育て直す大切な時間になるはずです。
(終)