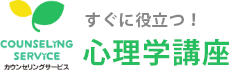実は、わがままの正体は自立して頑張る人ほど抱えやすい「依存心」の反動です。
自分を責めるのをやめ、愛を「もらう」側から「与える」側へとシフトして、愛し上手になる秘訣をお伝えします。
わがままな私が「愛される私」に変わるコツは「与える」こと
恋愛に苦手意識を感じている人の中には、「大好きな人と両思いになれた途端、自分が驚くほどわがままになってしまった」という苦い経験を持つ方がいらっしゃいます。
「あれやって」「これやって」と、相手に対して命令口調になってしまったり、思い通りに動いてくれない相手に猛烈に腹を立ててしまったり・・・。
「恋愛をすると、自分が悪魔に豹変してしまう気がする」 そう感じて、恋を遠ざけてしまっていませんか?
でも、あなたは決して悪魔ではありません。 わがままになってしまうのは、それだけその人のことが「大好き」だったから。
今日は、その「大好き」という思いを上手に表現し、愛し合えるあなたになるための「心のコツ」についてです。
◆大好きな人にわがままになってしまう心理的な理由
大好きな人にわがままになってしまう理由として代表的なのは、「愛されていると感じたい」という強い欲求です。
恋愛中なら当たり前の欲求ですが、表現方法を間違うと、二人の関係は崩れやすくなってしまいます。
□「愛されている」という証拠が欲しくなる
私たちは、愛されていることを実感したくて、色んな「おねだり」をします。
・「愛してると言ってほしい」
・「指輪を買ってほしい」
・「休みの日はいつも一緒にいてほしい」などなど。
しかし、たとえこれらがすべて叶ったとしても、なぜか心は満たされず、「まだ足りない」「彼のここがダメだ」と、愛されていない理由ばかりを探してしまうことはありませんか?
これはあなたが自分勝手だからではありません。 「何かをしてもらうことで、愛されていると感じられるはずだ」という、ちょっとした誤解をしているだけなのです。
□親密な人にほど「依存」しやすくなる理由
この誤解は、赤ちゃんの頃の体験にまでさかのぼります。 赤ちゃんはお腹が空いたりオムツが汚れたりすると、泣き叫んで誰かに助けを求めます。そして誰かにミルクをもらい、オムツを替えてもらうことで気分が良くなります。
このように「人に何かをしてもらうことで、自分の気分を整えようとする」状態を、心理学では「依存」のフェーズと呼びます。
成長していく中で私たちは傷つき、もう誰にも頼らず自分の力でなんとかしようと頑張り「自立」のフェーズへと進むのです。しかし、自立したからといって「依存心」が消えたわけではありません。
むしろ、「外で自立して頑張っている人」ほど、心を許した親密な相手の前では、心の奥にしまい込んでいた「依存心」が反動として爆発しやすくなるのです。それが、大好きだからこそ出てしまう「わがまま」の正体です。
◆欲しいものは「差し出す」ことで手に入る
「何かをしてもらわなければ、愛されているとは言えない」という誤解を解くには、私たちの心のしくみを知る必要があります。
心のしくみは、物理的な世界とは反対に、「与えるほどに増える」という特徴があります。
例えば「リンゴ」は、人に分けてあげると自分の手持ちは減ってしまいます。 しかし、心の中にある「優しさ」や「愛」はどうでしょう? 誰かに優しくしたからといって、あなたの優しさが減ることはありません。むしろ、優しくしたあなた自身の心の中にも、温かな優しい気持ちが増えていくはずです。
□「不足感」を埋めるための最短ルート
「愛されていると感じたい」と思うとき、心は「愛が足りない」という不足感を感じています。 その不足感を埋める唯一の方法は、皮肉なことに、もらうことではなく「自分から愛すること」なのです。
◆大好きな人にわがままにならずにいるためには?
大好きな人に「大好き」をまっすぐ伝えるコツは、相手を愛そうとすることです。 具体的には、こんなことから始めてみませんか?
□「この人は、何を喜ぶ人なんだろう?」と興味を持つ
私たちはつい、「相手が嫌がることはしないようにしよう」と考えがちです。 それも大切ですが、それでは「嫌われなくてよかった」という消極的な安心で終わってしまいます。
一歩進んで、「彼は何に喜ぶ人なのかな?」と興味を持って接してみてください。
「これかな?」と思ってやってみて、相手の喜ぶ顔を見る。 すると、あなた自身の心も「依存」の苦しさから解放され、喜びで満たされていくでしょう。
《最後に》
大好きという気持ちは、愛してもらおうと必死になるよりも、「愛そう」とすることで、相手にずっと伝わりやすくなります。
そんなことを繰り返しているうちに、あんなにわがままばかり言っていたのが嘘のように、あなたは最高の「愛し上手」になっているはずですよ。
ご参考になりましたら幸いです。
(完)