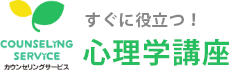親の願い
「自分に自信を持つ子になってほしい」
「自己肯定感の高い子に育てたい」
そう願うお父さんお母さんは多いと思います。
「自分はダメな子」
「自分なんて役立たず」
我が子が自分のことをそんな風には思うようになったら、いたたまれない気持ちになるのではないでしょうか。
では、どのように子どもと関わると子どもの自信が育つのでしょう。
子どものネガティブな感情にどう接する?
コマ(補助輪)なし自転車、飛び箱、鉄棒。
子どもたちには、いろんなことに果敢にチャレンジしてほしいと願います。
恐れずにサクサクこなしてゆくチャレンジ精神旺盛な子もいれば、緊張や不安、怖れなどのネガティブな感情が出てきてなかなか挑戦できずにいる子もいます。
我が子が怖がっていろんな物事に挑めないとき、子どもがリラックスできるように
「緊張しなくても大丈夫」
「出来ると思えば出来るよ」
「肩の力を抜いてー」
そんな言葉をかけたくなるかもしれません。
でも、実はそのような声掛けは、子どものネガティブな感情を否定していることになるのです。
力を発揮できない原因
親や大人である私たちは、ネガティブな感情は良くないと考えている人は多いのではないでしょうか。
緊張や不安、怖れを感じるのは自分が弱いからとか、不出来だからと捉えがちです。
けれど、誰でも初めてのことにチャレンジするときは、ドキドキと緊張したり恥をかくかもと不安になったり、失敗したらどうしようと怖くなるのは自然なことです。
子どもが自分の力を発揮できないのは、緊張や不安、怖れを感じているからではなく、その【ネガティブな感情を感じている自分はダメだ】という”自己否定”が原因なのです。
ネガティブな感情を肯定する声かけ
子どもがなにかに挑戦しようとしているけど不安で動けなくなっているとき、その不安な気持ちを子どもにしっかり認識させてあげます。
挑戦したいという思いと不安という感情のギャップは大きな負担になるので、思考と感情を一致させるのです。
「不安を感じているのかな? 不安を感じるのはダメなことじゃないよ。
でもちょっと勇気をだしてがんばってみようか」
そんな声掛けをすると子どもは【不安な自分でもOKなんだ】と安心してチャレンジという行動に移せます。
たとえ失敗したとしても覚悟を決めて挑む。
それが子どもの自信になるのです。
「不安だったけどチャレンジした自分」「不安がありながらベストを尽くした自分」
これは子ども自身の自己イメージが高まります。
もしも、失敗をしたときは失敗したことを受け容れる。
ここでも悔しさや敗北感を感じるかもしれませんが、それをダメなことと捉えずにそのまま受け止めることが大切です。
そのネガティブな感情を小さくしたり無かったことにしたりして誤魔化さず、ちゃんと向き合うことで同じ失敗を繰り返しにくくなります。
成功体験を積み上げよう
成功体験とは結果が上手くいくことではなく、ポジティブな感情、肯定的な感情を伴った体験のこと。
たとえ失敗したとしても、それはそれと受け止めその自分を否定しないということです。
とはいえ、無理難題な目標を掲げてその目標をいつまでも達成できないとしたら、自己否定感が強まって本来の力が発揮できなくなってきます。
なので、がんばれば確実に子どもがクリアできる目標を設定することも大切です。
たとえば 「今日は飛び箱の前まで走って行けたらOK」など。
そして、それができたら「飛び箱嫌いって言ってたけど、前まで走ってこれたね」など、小さなことでもちゃんとほめてあげることです。
言葉で伝えてもらうことで、子どもは自分のがんばりを見守ってくれている、わかってくれているという安心感と信頼感も育みます。
そして「うまくできた!」そう感じる小さな成功体験を何度も繰り返すことでモチベーションもあがります。
これは、大人にもいえることです。
ネガティブな感情は不快なのでダメなものや悪いもののように扱って、自分のありのままの感情を否定しがちです。
そうすると、子どものネガティブな感情も受け入れ難くなります。
あなたはどうでしょうか?
どんな感情も否定せず受け容れているかどうか、よかったらチェックしてみてくださいね。
*
来週は、朝陽みきカウンセラーがお送りいたします。
どうぞ、お楽しみに♪