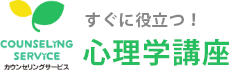子どもとずっと一緒にいると、子どもに振り回されるような感覚になることがありますよね。
子どもが評価されると、自分のことのように嬉しくなるけれど、逆に、子どもがつまずいていると、苦しくなったり、自分がダメな母親のように感じてしまう、なんてことが起こったりもします。
そんなふうに、子どもとの境界線が曖昧になる、母子関係の距離について、今回は書いてみたいと思います。
子どもと自分がくっつきすぎて起こること
たとえば、子どもが学校で叱られたと聞けば、まるで自分が叱られたように胸が痛くなり、子どもが頑張って賞をもらえば、自分が褒められているように誇らしくなる。
そんな経験、ありませんか?
また、小児科や習い事の先生とのやり取りで、気がつくと子どもに代わって、全部、自分が答えてしまっているとか。もちろん、子どもがまだ幼い頃は、それが当たり前で、むしろ必要な場面が多いでしょう。
でも、子どもが成長してきたとき、自分がそのような位置から降りられなくなっていることに、ふと気づく瞬間がやってくることもあります。
私自身も、小児科の先生が子どもに聞いていることに対して、無意識に、私が答えていて、先生から「お子さんに聞いてます」って、ピシッと言われて、ハッとなった経験があります。
こんな現象もあります。「主語を抜いて話す」母親。
子どもの話をする時に、主語(娘が、息子が、子どもが)を抜いてしまうため、聞いている人は、話をしている母親のことだろうと思って聞いていたら、子どもの話だったと、辻褄合わせでわかる、みたいなことも起こったりします。
無意識ですから、本人は気が付いていないですし、わざわざ指摘するのもなーと、周りもスルーしがちですが、意識してみると、結構、やっているお母さん、多いです。ペットちゃんの主語を抜いて話す人にも会ったことがありますよ。
いずれにせよ、誰かとの距離が近すぎると起こることです。
近いんじゃなくて、近すぎるんです。自分なのか、子どもなのか境界線が曖昧で、一緒になっている感覚です。
いつのまにか、子どもの宿題に入り込んでしまう
子どもの宿題のドリルや、習い事などを、子どもがやりたがらなかったり、うまくできなかったりする時、母親が、それらを積極的にやり始めることがあります。
代わりにやってあげているという意識はなくても、子どもにやらせたい、やって欲しい、成果を上げたい、といった母親の気持ちが、子どもではなく、自分を奮い立たせて、自分を突き動かすことで、それを叶えようとしてしまう心理です。
本来、子ども自身が取り組むべき課題に、親が「我が事」として入り込んでしまうのです。それが悪いわけではありません。小さい頃は、そうやって、見せてやることも、愛情の形でもありますし、リーダーシップをとることで、子どもをやる気にさせられることも、実際あったりしますから。
でも、子どもが成長してきた時、「この子の課題は、この子のもの」と線引きすることは、とても大切になります。そして、この線引きは、子どもを信頼することでしか、叶えられません。
子どもの成績や評価が、自分の評価のように感じてしまう。
うまくいかないと自分を責め、うまくいくと安心する。それは子どもを支えたい気持ちの裏返しでもありますが、自分の中のコンプレックスや、無価値観とセットになっていることも少なくありません。
自分の中のそういったものが大きいと、自分の子どもも、そうなるかもしれないと心配になります。そしてそれを避けるために、厳しくしつけたり、勉強を強要するようになることも。
子どもへの信頼は、自分への信頼と深く関わっているといえます。
子どもの力を信頼できず、手を出しすぎてしまうことで、却って、子どもの自立を妨げてしまうこともあるんです。
ほんの少し、子どもとの距離をみつめてみる
ここまで、読んでいて、ハッとされた方も、アタタタ、私のことだーと思った方も、いらっしゃるかもしれませんね。私もそうだったので、よくわかります。
今の自分の子育てについて、少しだけ、振り返ってみるのはいかがでしょうか。子育ては大変で、忙しいです。立ち止まること自体、とてもむずかしいことですが、ほんの少し、子どもとの距離をみつめてみましょう。
あ、でも、反省会は開催しなくていいですよ。自分責め大会もしないでくださいね。気づくだけでいいんです。気づくだけで、大事な部分は半分終わっているといってもいいくらいなんですから。
・子どもが聞かれていることに、口を挟んで、子どもに答えさせていなかったことは、なかったかな?
・子どもでは、きっとうまく答えられないだろうって、思い込んでいなかったかな?
・勉強が苦手な私のコンプレックスのせいで、不安になって厳しくしすぎてなかったかな?
・主語、どうなってたかしら??
気づければ、止められるものなんです。
私もあれ以来、小児科では、お口にチャックしてましたよ。
子どもを信じる、自分自身を信じる
子どもを“自分とは違う一人の人間”として信頼する。これは、言葉では簡単ですが、実践するのは、なかなかむずかしいものです。子どもが小さければ、なおさら。
子どもは、母親が思うよりもずっと、強くて、賢くて、自分の力で道を切り拓いていく存在です。でも、母親が「この子はまだまだ」と思って、助け舟ばかり出してしまうと、子どもは「自分は信じてもらえていない」と感じてしまうかもしれません。
自分でやる気も起こらなくなってしまうかもしれません。
逆に、子どもが失敗した時に「自分が悪かった」「ちゃんと教えられなかった」「私の子育てはまちがっていた」などと、自分を責めすぎることもまた、母子関係がくっついているために、起こりやすいものです。
大切なのは、「この子は大丈夫」と信じてみること。そして、「私も子育て、がんばってる」「ベストを尽くしてる!」と、自分自身のことも認めて、信じてあげることです。
子どもの人生に現れる障害物を、全部、前もって取り除くなんて、不可能なことです。それよりも「きっと大丈夫」って、思ってあげられること。応援してあげられること。すると、親に信頼された子どもたちは、安心してがんばれるんじゃないかと思います。
母子癒着から始まるのはわるくない
子どもと一緒にいる時間が長いからこそ、母子の距離感が曖昧になるのは、自然なことです。でも、子どもが成長していくにつれて、親もまた、子どもとの距離を考え直すタイミングがやってきます。
子育てがしんどいなって感じる時には、子どもとの距離感について、気づけることがないかチェックしてみましょう。
母子癒着なんて聞くと、ちょっとイヤな感じがしますけれど、実は、日本の文化の特徴でもあり、人生の最初に、おかあさんとしっかりくっついて、ぬくもりや愛情をもらっていた。(ウザいくらいに)そして、そこから自立が進んでいくというのは、順番としては、ベストなのではないかと、私は思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
お役に立つことがあれば、嬉しいです。
来週金曜日は、いしだちさカウンセラーがお送りします。
どうぞお楽しみに。