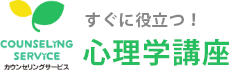いつもビジネス心理学講座の記事を読んでいただきありがとうございます。
カウンセリングサービスの伊藤顕市です。
私が20代前半の頃、職場の研修としてあるセミナーを受講しました。
その中で、10数年経った今でも印象に残っている実習がありましたので紹介したいと思います。
それは「赤黒ゲーム」というものです。
赤黒ゲームとは、2つのチームに分かれ、チーム内で話し合い、相手チームに「赤」「黒」のどちらかを投票し、開票の結果に応じた点数を獲得して高得点を目指すというゲームです。
投票結果が双方「黒」の場合、両チーム3点をプラス。
双方「赤」の場合、両チーム3点をマイナス。
「赤」と「黒」の場合、「赤」を投票したチームが3点プラス。「黒」を投票したチームが5点マイナス。
これを数回繰り返して合計点を出します。
ゲーム開始前に司会者から、
「このゲームの目的は、勝つことです。勝ち方は、合計点により多くの点数を蓄えることです」
とだけ説明されます。それに加え、ゲームの事を知っている人は、発言を控えるよう案内されます。
仮にこちらが「赤」を出し、相手が「黒」を出した場合、3点を獲得し、相手は5点失うので、相手より多い点数を獲得することができます。
相手が同じように「赤」を出したとしても双方3点を失うことになるので負けることはありません。
お互いに「黒」を出し合えば3点ずつ獲得できるのですが、「このゲームの目的は、勝つことです」と言われているので、相手チームより多い点数を得ようとして、「赤」を投票する傾向があります。
しかしながら、このゲームなりの正解は、「黒」を投票し続けて両チーム共に高得点を獲得すること。としています。
確かに双方が「黒」を投票し続ければ、互いに最高得点を獲得できます。
「勝ち方は、合計点により多くの点数を蓄えることです」との説明も、自身のチームだけでなく相手チームの合計点も含めるのであれば、双方が「黒」を投票する以外にありません。
説明が不十分なのですが、限られた情報で「勝つ」という言葉から相手より多くの点数を得ようとします。
中には、
「相手が何を投票するのかを読み合うゲームだ」
という、「このゲームの目的は、勝つこと」という目的以外の解釈をしてしまう人もあります。
ところが、司会者から
「あなた達は相手を負かすことばかり考え「赤」を投票した。日常生活でも同じ事をしていませんか?」
というレクチャーをされます。
「日常生活の目的も勝つこと。勝ち方は、合計点により多くの点数を蓄えること」
と念を押されたように思います。
この実習は、勝つことを目的にしていますが、実際には勝つどころか、双方が満足できるWINーWINの関係になれていないこと、互いに足を引っ張りあう関係になってしまっている事を思い知るものになりました。
日常生活に置き換えると「黒」は、“思いやり”や“優しさ”や“誠実さ”といったポジティブなもの。
「赤」は、“身勝手”や“意地悪”や“裏切り”といったネガティブなものではないでしょうか。
他者を差し置き、私利私欲による自分勝手な行動を無自覚にしてしまっている事に気付かせるような実習なのかも知れません。
他の学びとして、「目的は、勝つこと」から「相手の思考を読み合う」というように、先入観などによって認識が歪んでしまう現象。「認知バイアス」を目の当たりにしました。
「赤」の投票をされた後には、こちらからも「赤」を投票したくなる「返報性の法則」も感じ取ることができました。
チーム内で何を投票するか話し合う中でも、同調圧力により自分の意思が掻き消される体験もできました。
私なりに多くの学びを得ている赤黒ゲームは、今の私の日常生活の中でも役に立っています。
それは、“相手に「黒」を投票する判断材料”になっているということです。
ついつい相手に「赤」を投票したくなることもあります。
そんな時は、この赤黒ゲームを思い出すようにしています。
「目的は勝つこと。勝ち方は、より多くの点数を蓄えること」
“勝つ”という言葉を使うと、どうしても勝者と敗者を意識してしまうので、
「目的は豊かになること。豊かになる方法は、より多くのポジティブを選択すること」
と私なりに言葉をアップデートしています。
そうは言っても、何が「黒」なのか分からなかったり、悩んでしまうこともあります。
相手に「黒」を投票したつもりでも上手く行かない事もあるでしょう。
それでも「赤」を投票して私自身が罪悪感を感じたり、嫌な気持ちになって後悔しないため、自分が納得して「黒」を投票するための私なりの判断材料にしています。
私なりの解釈ですが、この記事が少しでも何かの参考になれば幸いです。